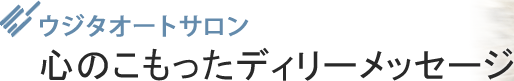2011/02/17 ちょっとしたお話

これは、先日、夜釣りの船上での写真、、、、、
当日の成果は、、、まず一番手は

続いては、、、
何故か「伊勢えび」が、、、????

じつはここは、大阪の繁華街、
『難波のど真ん中』での釣り舟・居酒屋でした。

昨年の打ち上げ!
そして、本年の景気つけ!のつもりが、、、
すっかり、皆でよいつぶれて、、、、、、、、
その後の事はまた、ゆっくりと、、、
関西1号店・釣船茶屋ざうお難波本店
http://www.zauo.com/contents/zauo_nanba.html
魚釣り好きな方に話すと、さっそく親子孫でしっかり楽しんできたそうですョ。
2011/01/28 ちょっとしたお話
昨夜、保険会社の三井住友の新年研修会で
嵐山に有る、宝厳院と弘源寺の住職、田原義宣師にお説教を授かりました。
(寶厳院http://www.hogonin.jp/)
宋の時代の禅僧、五租法演が、自らの弟子に贈ったとされる、
『法演の四戒(ほうえんのしかい)』についてです。
勢不可使尽
1、勢い使い尽くさば、禍(わざわい)必ず至る。
福不可受尽
2、福受け尽くさば、縁必ず孤なり。
規矩不可行尽
3、規矩行い尽くさば、人必ずこれを繁とす。
好語不可説尽
4、好語説き尽くさば、人必ずこれを易(やす)んず
であります。
内容についてはご興味があれば、一度勉強して見てください。
私事ですが、はじめて天龍寺に座禅に行ったのは33年ほど前の27歳の時です。
何かにつけ悩みの多いその頃、何度もそこで道を示して頂けたからこそ、今日が有ると自覚致しております。
http://ujita.co.jp/blog-diary/2007/11/24/%ef%bc%99%e3%80%81%e3%80%8c%e6%88%90%e5%8a%9f%e3%81%ae%e5%8f%8d%e5%be%a9%e3%80%8d/
今回、田原義宣師に講演をお願いしたのも、久しぶりに聞かせて頂いたのも、
こんな時代だからこそ、で有ります。
またまた、勉強になった想いの氏田耕吉ですが、
もう少し身に落してから、続きを報告させて頂きます。
失礼しました。
2011/01/27 ちょっとしたお話
こんにちは、工場の青木です。
先日、サイクリング中に出会ったワンちゃんと、とんどやきの準備をしているオジサンたちです。
川沿いでとんどやきの準備中の一こまです。

すこし離れての図。

河沿いの遊歩道で出会ったコーギーの、
ここちゃん、4才 すごく人懐っこい女のコ

ぎゃろくん 11才 はにかみやさんですが、おいでおいですると寄ってきてくれました。

2011/01/18 ちょっとしたお話
寒の入り。
冬本番を迎えた。
「新年を迎えると気分も変わる」と言われ、
景気がよくなることを期待したいところだが、
寒風吹く日本市場に訪れる春はまだ先となりそうだ。
今年一年、幸福を呼ぶために心がけたい七つの言葉を飲み込んでみる。
第一は「笑顔」。
ことわざ「笑う門には福来る」の通り、
心身ともに健康であるための基本として改めて実践していきたい。
二つ目は「夢」。
「たわいのない夢を大切にすることから、革新が生まれる」(井深大)と
いうように小さくても前進する力となる。
合わせて、その夢への一歩を踏み出す
「勇気」を持ち、前向きに行動したい。
4種目は「誠意」。
「どの種の困難であれ、これを乗り越えていく最大の武器」(神谷正太郎)として携えたい。
そして「人に与えて、己いよいよ多し」(老子)。
「奉仕」 の姿勢を忘れずに謙虚な気持ちを持ち続けたい。
スパイスとして 「遊び心」 も加えたい。
効率を追求する中で切り取られがちだが、
楽しむことが次へのパワーになる。
最後に、「小さいことを重ねることが、とんでもないところへ行くただひとつの道」(イチロー)というように、どんな天才にも必要な
「努力」 は欠かせない。
日刊自動車新聞の霧灯から、、、

2011/01/13 ちょっとしたお話
最近のベルトは強くてなかなか切れないんですけど
今回ベルトテンショナーのベアリングが焼き付き
ベアリングがロックされてしまったために
焼き切れたベルトに出会ったので資料のため撮った画像です。


何か一つでも部品の性能がかけると
他の部分に必要以上の負荷が集中してしまい
どこかが破綻してしまう。。。
見事に切れたベルトを見てると、
設計した人の素晴らしさに
思わず感心してしまった今日この頃でした。
Comments: コメントは受け付けていません。
Tags:
2011/01/13 ちょっとしたお話
「○○だけダイエット」という物に、めっぽう弱い。
しかし世の中、そう甘かない。
「100キロメートル走るだけダイエット」とか「1週間断食するだけダイエット」とかが登場しても、飛びつかないよう注意したい。
と、言ってるそばから、また飛びついた。
今週のお題「ダイエットシューズ」だ。
これも「○○だけダイエット」の仲間みたいなもの。
歩くだけでエクササイズの効果があるウォーキングシューズのことを言う。
スポーツメーカーなどからいろんなダイエットシューズが出ているが、だいたい仕組みはこう。
靴の底を膨らませるなどして、履き心地をわざと不安定に。
一歩ごとに筋肉を鍛え、お尻や太ももなどをシェープさせる。
まあ、靴にバランスボールをくっつけて歩く、みたいなイメージ。
とはいえ、もちろん見かけは普通の靴。
ここ数年、米国から人気の火が付き、おじさん向けの通勤靴風から、おしゃれにうるさい女子向けまで、デザインも豊富にそろっている。
たしかに歩きにくいが、すぐ慣れる。
しかも長時間歩くと、お尻の肉など、珍しいところが筋肉痛に。
効いている!
2010/12/30 ちょっとしたお話
新年の挨拶で自宅を訪問する際、駅からタクシーを利用したら、
玄関先ではなく少し手前で降ります。
ブザーを鳴らす前に手袋やマフラーを取り、
コートを裏返しにたたみ、腕にかけ身だしなみを整えます。
ブザーの押し方にも人柄があらわれます。
立て続けに鳴らすようなことは無粋です。
上がる際は、玄関の正面から前向きに上がり、
お迎えの人に自分の真後ろを見せないように、
膝つきに座り、靴をすぐ履ける形になおして端に置きます。
コートは、外のほこりを落とさないよう裏返しにたたんでいますので、
部屋の中には持ち込みません。
玄関の邪魔にならないところに置きます。
洋間では立って、和室では畳に座って(座布団には座らず)新年の挨拶をします。
そのあとお土産を紙袋や風呂敷からとって渡します。
風呂敷も、松や鶴亀など、縁起のよい模様のものを利用すると
気がきいています。
勧められたら椅子に座るなどします。
座布団は決して踏んで座ることがないように。
下座側に座ってからにじり上がります。
家や庭、お子さんや近所の環境などよいところを見つけて褒めると
喜ばれますので、心に留めて話題にしましょう。
門までお見送りされた時は、歩きだしてから、
一度は必ず振り返ってお辞儀をするようにします。
コートは、勧められたら玄関で「お言葉に甘えて、失礼します」と言って着てもよいです。
マフラーや手袋は外に出てからです。
コラムから、、、